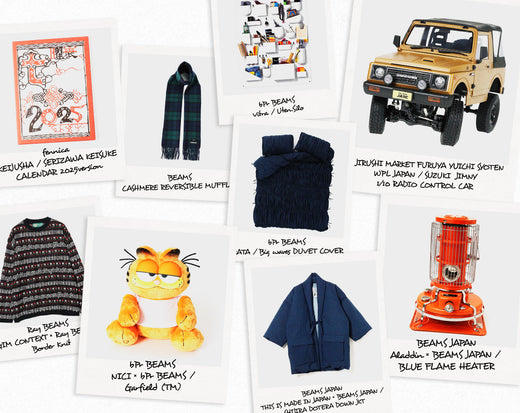HANG OUT VOL.4 SKI & CHRISTMAS
皆川賢太郎さんに聞く、
スキーの過去・現在、そして未来。
スキーはスポーツとレジャーの側面を持ち、自分を追い込んで滑るひとがいれば、楽しく滑るひともいる。どちらにせよ、舞台となるのはスキー場。全盛期から30数年経ち、スキー場やスキーヤーはどのように変化したのだろう。冬季オリンピックのアルペンスキーに4大会連続で出場し、現在はリゾート開発など冬季産業の発展に尽力している皆川賢太郎さんに話を訊く。いま、スキーは新境地に立っている。
PROFILE
皆川賢太郎

1977年生まれ、新潟県湯沢町出身。元アルペンスキー日本代表。世界選手権やワールドカップなど、数々の大会に出場。1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピックに日本代表選手として出場。2006年トリノオリンピックでは4位を記録し、日本人として50年ぶりの入賞を果たす。2014年に引退。現在は一般財団法人「冬季産業再生機構」代表理事を務め、岩手県の安比高原スキー場や新潟県の苗場スキー場のコンサルティングも手がける。
幼少期から現役時代の思い出。
―皆川さんは3歳からスキーを始めたそうですね。
皆川:実家が苗場でペンションを営んでいて、家のドアを開けると、すぐにスキー場だったんですよ。だから、子どもたちが公園でサッカーや野球をして遊んでいる感覚でスキーをやっていました。
―スキーのどんなところに魅力を感じていましたか?
皆川:滑降するのが楽しかったんだと思います。自分の力でコントロールしてスピードを出すことが楽しかった。朝からナイターまで滑っていて、親には「飽きないの?」って言われていたくらい(笑)。
―アルペンスキーは何歳から始めたんですか?
皆川:もう記憶にありませんが、小学2年生のころ新聞の取材を受けて「オリンピック選手になる」と答えていました。アルペンスキーは、決められたコースを誰が1番速く滑れるか、とにかく速さがものを言うシンプルなルール。タイムを競うのも好きだったので、それも魅了された理由だと思います。
―そのときは、誰かに負けたくないという気持ちがモチベーションになっていたんですか?
皆川:小学5年生のとき、サマースクールで初めてオーストリアへ行ったんですよ。地元ではスキーが上手なほうでしたが、海外には自分以上にうまい子が何人もいて。年齢を聞いたら、同級生とかひとつ下。それがライナー・シェーンフェルダー選手とベンジャミン・ライヒ選手でした。
―2006年のトリノオリンピックで表彰台を争った2人ですね。
皆川:その出会いは大きかったです。中学から大学まで、ずっと2人の存在が頭にあって、もっと速くなっているんだろうなと考えていました。
―小学5年生以来の再会は、トリノオリンピックだったんですか?
皆川:いいえ。高校生になってから、世界ジュニアで久しぶりに顔を合わせて、向こうもぼくのことを覚えていたみたいで話しかけてくれました。毎年試合で会うようになって、次の大会についてとか、イタリアのレストランが美味しかったとか、あのホテルがよかったとか、教えてもらっていました。ぼくたちが試合をするのはリゾートで、ホテルやレストランが日常にあったので、それも好きになっていって、現在の仕事に繋がっています。